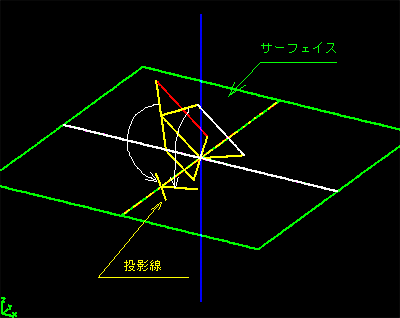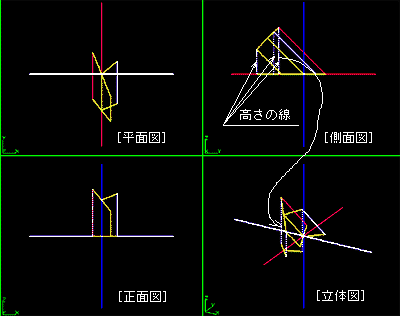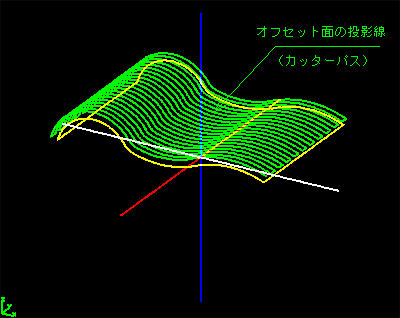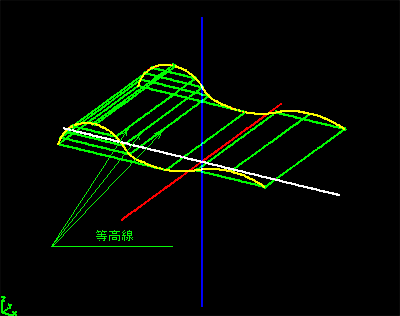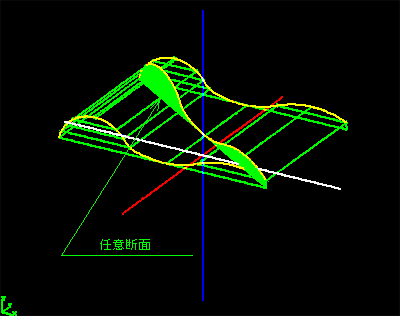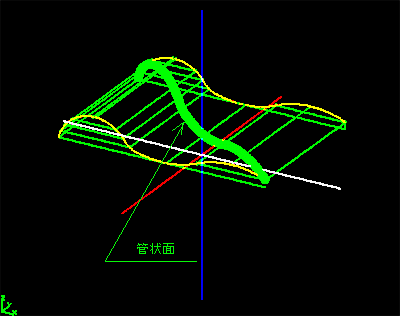高度なモデリングとCAM
3次元モデリングの基礎・実践を読まれた方は、ご苦労様でした。
ここでは、作った3次元モデルの利用法を解説します。
本当は、2次元と3次元のどちらが簡単か?は、賛否が有ると思います。
しかし、作ったモデルの利用法となると、私は明らかに3次元を支持します。
CADのデータを、図面以外の用途に利用出来る。
それが、プロダクトモデルの概念だと思うから…。
1、立体の2次元投影
3次元で作ったものを2次元に投影する。
一見、無意味なようなこの操作が、実は、もの作りには大切な事が有ります。
構造物と名が付けば、それは大地(2次元面)に設置される事が大半です。
その際に、変形した構造物は、組み立て時の検査が大変です。
どこを検査したら良いのか、そもそもどうやって検査したら良いのか。
そんな時に、3次元モデルが有ると、この点とこの点をメジャーで計れ、という指示が出来ます。
CADの中でシュミレートしたモデルと、現物の照合が出来るからです。
ここで、例として実践編で作成したCT鋼を取り上げましょう。
CT鋼を地面に設置しました。さて正しく設置出来たでしょうか?
それを確かめる資料作りのお話です。
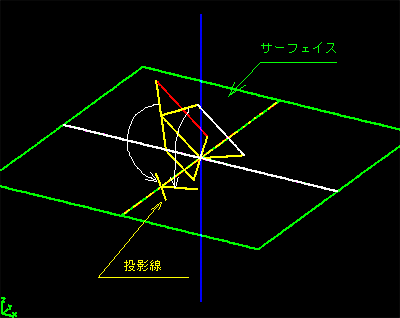
①:平面のZ=0の位置に面を作成する。
②:作成した面に、CT鋼の上面(矢印部)を、真上から投影する。
ポイントは、真上から投影という事です。
真上から投影すれば、CT鋼上面の地面での位置が即座に分かります。
もし、その位置がCT鋼の下面と重なれば、その位置の高さは、メジャーで計れません。
(その位置には、地面が無くなっているからです。)
余談ですが、その位置は、太陽が真上に来たら影になる箇所でもあります。
もっと低い角度から投影すれば、影がどこまで及ぶかもシュミレート出来る。
投影の意味を、ご理解頂けたでしょうか。
では、何故、投影すれば、高さが計れるのか?という問題です。
2、投影点と上面の点間は最短距離
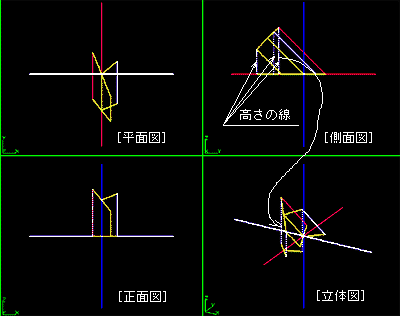
側面図の”高さの線”と表現した線に注目して下さい。
これが、投影した3点と、CT鋼の上面の3点を結んだ線です。
この直線の長さが、CT上面の3点の高さなのです。
この位置に重りをぶら下げた糸を垂らせば、同じ長さが必要なはずです。
真上から投影した、と言う事は、重力の方向へ投影した事にもなります。
最新鋭の光波測定機が無くても、釣り糸と重りで検査が出来る。
デジタル、精密の時代でも、道具は使い方の典型かと思います。
勿論、最新鋭の機械が有れば、様々な角度から計測も出来るでしょう。
(第一、釣り糸だと、重りで糸自体が延びますし…。)
でも、計測した数値が正しいのかどうかを知るには、シュミレートが早い。
もっと言えば、シュミレートした数値になるように、組み立てれば良い。
いわば、3次元モデル=シュミレーションモデルでもある訳です。
3、NC工作機のデータ
ここで、発想の転換です。
真上から地面に作成した面に線分の投影が出来ました。
では、CT鋼自体に面を作成して、上から線を投影したらどうなるでしょう?
ポジ面とネガ面が分かるから、雨が降った時、濡れる濡れないの範囲が分かる。
この発想が、NC工作機用データの作成に利用されています。
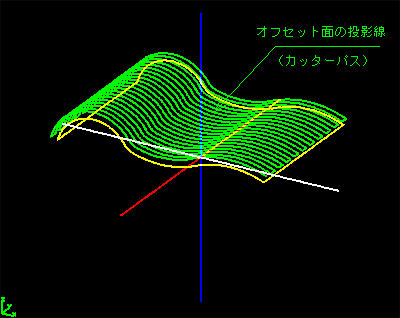
NC工作機とは、真上(真横)から、工作物を削ったり、つないだりします。
横の画は、実際に金型を切削する際に使用される、切削具の軌跡です。
(工具の軌跡の事を、カッターパスと言います。)
この位置を工具の中心が通れば、真角の工作物でもなだらかな表面に削れる。
そのために、完成状態のモデルを工具中心までオフセットした面を作ります。
そのオフセット面に真上から縦横の線分を投影すれば、切削具の軌跡が出来るのです。
後は、その軌跡通りのNCデータを作って機械に任せれば、複雑な加工も思い通り。
何回でも、同じ物が作れるのも強みでしょうか?
また、どこがネガ面かも分かっているので、工具を45度傾けて…の対応も出来ます。
削ってみたら必要な形状が無くなって、工具が宙を走ってた…は、嫌ですものね。
ただし、この軌跡を求めてNCデータに変換するソフトは高価です。
CADが50万円ならば、CAMと名の付くソフトは500万円でしょうか?
また、近年は、逆オフセット法やらソリッドを利用した作成方法も有るようです。
しかし、いずれも3次元モデルを利用する概念は同じ。
多分、3次元モデルの利用法としては、一番進んでいると思います。
4、等高線作成
また、発想の転換です。
これまでで、投影は真上から行うものだと思われた方。
真横から、線分をモデルに投影したら…等高線が作れますね。
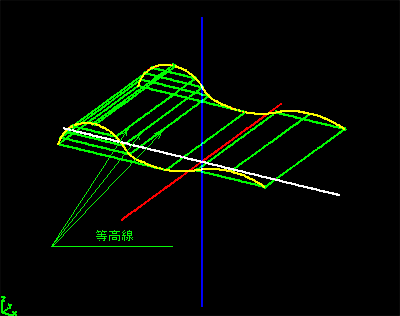
先ほどの金型用曲面モデルが、野山と仮定しましょう。
造成して平地を作る際、どこまで削れば良いかは問題です。
でも、等高線で断面を求めて、面積計算が出来たら。
CADは結構賢いので、一筆書き線内の面積計算が出来るのです。
多分、少し高価なCADならば、体積計算も出来るはず。
削った土砂の量と、得られる平面積が簡単に分かれば有り難い。
野山が海底ならば、どれくらいの土砂で埋め立てが出来るかも分かるはず。
CAD=精密計算だと決め付けないで、そんな利用法も考えましょう。
5、任意の断面を求める
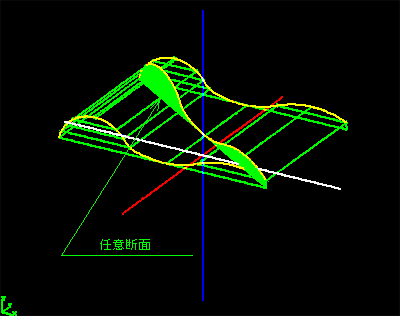
今度は野山に真上から斜め線を投影しました。
野山を横切る道を作るなどは、よく有りそうな話です。
では、道を作ったら、山肌はどうなるか?
山止めのモルタルは、どれくらい必要なのか?
そんな事も、任意の断面を作れれば、即座に分かるはずです。
問題は、野山を相手に、どうやってモデリングを行うのか?ですね。
これには、一つ考え方が有って、金型製作では、カッターパスから面が作れます。
それならば、人工衛星から得られたデータで、日本全土のモデリングも可能?
少し、話が飛躍しましたが、3次元モデルの利用法は多種多様。
最後にもう一つ、面白い利用法を紹介します。
6、管状面の作成
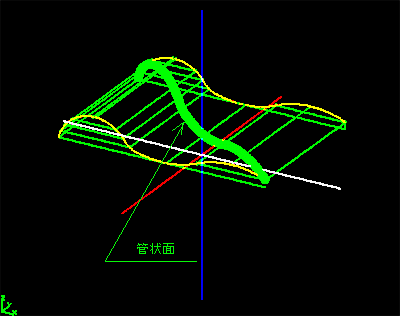
前述の野山に斜め線を投影した線…曲線ですが…。
これが、パイプの中心線だとしたら、どうでしょうか?
そんな、曲がりくねったパイプのモデリングなんて…。
ところが、これが案外簡単に出来るのです。
プラント設計で一番厄介なのが、縦横無尽に駆け巡った配管です。
全てが同じ径ではないので、パイプ同士の干渉に神経を使います。
しかし、パイプの芯だけ3次元でモデリングして、外形も簡単に作れるのなら…。
パイプの総延長や曲げ加工の資料まで取り出せれば、随分、楽になるでしょう。
いいことずくめの3次元モデリング。
でも、現実には、モデリング技術者が少ないことが最大の問題。
プロブリッジ、シンフォニ、Xスチール等々、3次元プロダクトモデラーが有っても、
使う人が2次元の感覚だと、難しく感じると思うのです。
せめて、基礎編の座標操作の感覚だけでも理解して頂けたら…。
ガリレオは、教会で地動説を否定せざるを得なくなった時、誓約書を書きながら、
”それでも、地球は動いてる。”と小声で言ったそうです。
10年前から比べれば、橋梁業界にも3次元必要論が増えました。
でも、皆がその必要性を認識しないと、前進は有りません。
是非、皆さんのご協力をお願いします!!!
3次元モデリングに戻る
メニューに戻る